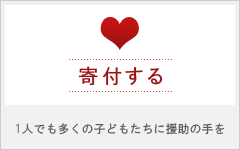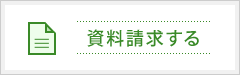2009/12/18
報告:KnKスタッフ 清水 匡

津波で半壊した家を改装してオープンされた食堂
2004年12月26日。スマトラ沖地震・津波でインドネシアのアチェでは16万人もの死者・行方不明者が出た。あれから5年。アチェの人たちはどうしているだろうか。
■パサールアチェ
各国の支援で様々な建物が新しく建てられたバンダアチェの町。パサールアチェ(アチェマーケット)にオープンした美しいショッピングモールの入口で日本の支援のマークを見つけた。中にはエスカレーターまであり、津波前のマーケットよりもきれいで品揃えも豊富になった。

津波以前よりもきれいに
なったショッピングモール
客足も増えたという
地方からの出稼ぎも増え、バンダアチェの町は以前にも増して活気づいている。商売も津波前と比較しても売り上げがいいらしい。しかし、みな口をそろえて言う。
「津波前よりもこの町は設備が充実し生活も豊かになった。そういう意味では今のほうがいい。しかし私たちは昔のバンダアチェの方が好きだった。」

日本の支援もいたるところで見られた

仕立屋のアブラフマさん
近郊の町シグリからの出稼ぎで仕立屋を経営しているアブラフマさん。病気で妻を失い男手ひとつで4人の子どもを育てている。平日は母親に子どもを預けて店を切り盛りし、週に一度、子どもと会うためにシグリに戻っている。
「津波で何もかもなくなってしまったこの町に活気が戻ってきたよ。少しだけどうちも売り上げが上がった。でもこの通り小さな店でね。誰か新しいミシンを援助してくれないかな。」と意味ありげな笑顔を見せてくれた。
■じっとしていると、家族のことを思い出す
タブラニさんは現在、地元NGO、CCDE(Center for Commmunity Development and Education)の代表を務めている。
彼は2004年12月26日の朝もいつもと変わらない時間に事務所へ出勤をした。その直後、大地震が発生し津波がバンダアチェの町を襲った。家族を案じ急いで戻ったタブラニさんが家があった場所に着いたとき、彼は言葉を失った。そこには何も残っていなかった。CCDEの活動も津波で一時中断を余儀なくされた。一瞬にして家と家族を失ったタブラニさんは、悲しさを紛らわせるためがむしゃらに援助活動に奔走した。「じっとしていると、家族のことを思い出して苦しくなるから」と語っていた。
2007年はCCDEの活動も再開し、自身も再婚した。彼にとっては再出発の年となった。そして2009年には子どもを授かった。
CCDEでは、女性を対象にマイクロファイナンスを提供し、経営についてのワークショップを行っている。物の売り方やお金の管理などをグループごとに意見を出し合い、話し合っている。実際に発言し人の意見を聞くことにより、物事を客観的に捉えることができるのだそうだ。CCDEはこのほかに、アチェで貧困に苦しむ人たちへ職業訓練を提供したり、女性の権利や家庭内暴力防止の啓発運動を行っている。そして月刊誌を発行し、こうした諸問題を世論に訴えかけている。

CCDEの代表、タブラニさん

意見を交し合う女性たち
■バラック
2005年当時は数十万の人々がバラック(津波被災者の仮設住宅)で生活していたが、今はそのほとんどが撤去された。
津波は海岸線をも飲み込み地形を変えてしまったが、水没した地域に暮らしていた人々に対し、政府は、山の方に建てられた家に移るよう勧めるだけだった。しかし山へ移ってしまっては漁師の仕事ができないため、多くがこのバラックに入居し現在に至っている。
ムアリマさん(22歳)はアチェ南東部の村の出身。津波の翌年、17歳で出稼ぎのためバンダアチェまでやってきて、その後、今の夫と出会った。現在は夫と2人の子どもと共にバラックで暮らしている。夫の実家は津波で家屋が流されただけでなく土地そのものが水沈してしまった。狭い仮設住宅に4人暮らしで生活は厳しいというムアリマさん。今後、自分たちの生活がどうなるか不安だと語っている。
ムアリマさんが暮らすバラックには8世帯が生活している。しかし、このバラックも今年12月には撤去されてしまうという。